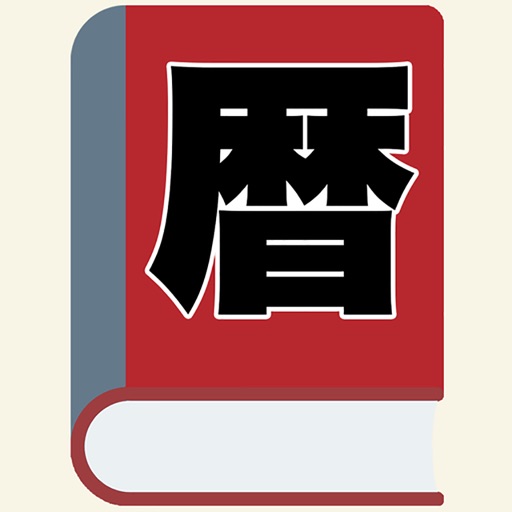算命学の歴史

ねこにゃん
うさ先生、算命学って占いっていうのは分かるけど、どんな占いなんですか?
算命学を知るには、まず算命学の歴史から話すね。
算命学は今から約2300年ほど前、鬼谷子(きこくし)という軍略家 が、陰陽五行思想(いんようごぎょうしそう)を元にして、算命学の原点理論を作り上げたといわれているよ。
算命学は今から約2300年ほど前、鬼谷子(きこくし)という軍略家 が、陰陽五行思想(いんようごぎょうしそう)を元にして、算命学の原点理論を作り上げたといわれているよ。

うさ先生

ねこにゃん
軍略ってことは戦いのために作られたの?
そう。中国王朝はこの優れた軍略を、自国の権勢を維持するための奥義として使っていたんだよ。その後、長きに渡って一子相伝、門外不出とされてきたよ。

うさ先生

ねこにゃん
へー。その後どうやって日本に伝わったの?
日本に算命学理論がやって来たのは、第二次世界大戦後だよ。
文化革命の弾圧を避けるため日本に退避してきた、 呉仁和(ごじんわ)氏から算命学理論を受け継いだのが、故・高尾義政(たかお よしまさ)先生だったの。
文化革命の弾圧を避けるため日本に退避してきた、 呉仁和(ごじんわ)氏から算命学理論を受け継いだのが、故・高尾義政(たかお よしまさ)先生だったの。

うさ先生

ねこにゃん
高尾算命学は聞いたことあるよ。
高尾算命学は昭和40年代に日本で公開されたの。
その後、天中殺(てんちゅうさつ)が大ブームになったこともあって算命学は大衆の中に徐々に浸透していったよ。
その後、天中殺(てんちゅうさつ)が大ブームになったこともあって算命学は大衆の中に徐々に浸透していったよ。

うさ先生

ねこにゃん
日本に入ってきたのは戦後なんだね。
勉強になりました。
勉強になりました。
算命学とは
陰陽五行思想(いんようごぎょうしそう)

うさ先生
じゃあ算命学について簡単に説明するね。
算命学とは陰陽五行思想(いんようごぎょうしそう)から出来ているもので、人を自然界に置き換えて分析する占いだよ。
算命学とは陰陽五行思想(いんようごぎょうしそう)から出来ているもので、人を自然界に置き換えて分析する占いだよ。
陰陽五行思想はどんなものなの?

ねこにゃん

うさ先生
まずは陰陽思想(いんようしそう)から話すね。
陰陽思想は、全ての物事はそれだけが単独で存在するのではなく、陰と陽という相反する形で存在する思想だよ。例えば明るい(陽)と暗い(陰)、男(陽)と女(陰)、晴れ(陽)と雨(陰)、生(陽)と死(陰)などだよ。
これを一極二元論(いっきょくにげんろん)というの。下記の図を見たことはないかな。
陰陽思想は、全ての物事はそれだけが単独で存在するのではなく、陰と陽という相反する形で存在する思想だよ。例えば明るい(陽)と暗い(陰)、男(陽)と女(陰)、晴れ(陽)と雨(陰)、生(陽)と死(陰)などだよ。
これを一極二元論(いっきょくにげんろん)というの。下記の図を見たことはないかな。

あるよ。このマークかっこいいよね!二つで一つってことだよね。

ねこにゃん

うさ先生
そう。よく知ってるね!
五行思想(ごぎょうしそう)は下記の絵みたいになるよ。くわしくは 「算命学を学ぶ上で大切なのは五行を知ること」を読んでね。
五行思想(ごぎょうしそう)は下記の絵みたいになるよ。くわしくは 「算命学を学ぶ上で大切なのは五行を知ること」を読んでね。
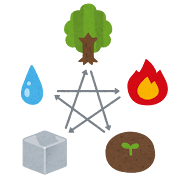

うさ先生
算命学では生年月日から出した命式の年、月、日に干支(かんし)が割り振られているの。
甲、 乙、 丙 、丁 、戊、 己、 庚 、辛 、壬 、癸( こう、おつ、へい、てい、ぼ、き、こう、しん、じん、き)の 十干(じゅっかん)と、子、 丑、 寅、 卯、 辰、 巳、 午、 未、 申、 酉 、戌、 亥 (ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い)の十二支(じゅうにし)で、干支(かんし)となるの。
この十干と十二支は陰陽に分けられるの。
甲、 乙、 丙 、丁 、戊、 己、 庚 、辛 、壬 、癸( こう、おつ、へい、てい、ぼ、き、こう、しん、じん、き)の 十干(じゅっかん)と、子、 丑、 寅、 卯、 辰、 巳、 午、 未、 申、 酉 、戌、 亥 (ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い)の十二支(じゅうにし)で、干支(かんし)となるの。
この十干と十二支は陰陽に分けられるの。
へーそうなんだね!どんなふうに分けられるの?

ねこにゃん

うさ先生
下記の図みたいに分けられるよ。
| 十干 | 五行 | 陰陽 |
|---|---|---|
| 甲 | 木性 | 陽 |
| 乙 | 木性 | 陰 |
| 丙 | 火性 | 陽 |
| 丁 | 火性 | 陰 |
| 戊 | 土性 | 陽 |
| 己 | 土性 | 陰 |
| 庚 | 金性 | 陽 |
| 辛 | 金性 | 陰 |
| 壬 | 水性 | 陽 |
| 癸 | 水性 | 陰 |
| 十二支 | 月 | 五行 | 陰陽 |
|---|---|---|---|
| 子 | 12月 | 水性 | 陽 |
| 丑 | 1月 | 土性 | 陰 |
| 寅 | 2月 | 木性 | 陽 |
| 卯 | 3月 | 木性 | 陰 |
| 辰 | 4月 | 土性 | 陽 |
| 巳 | 5月 | 火性 | 陰 |
| 午 | 6月 | 火性 | 陽 |
| 未 | 7月 | 土性 | 陰 |
| 申 | 8月 | 金性 | 陽 |
| 酉 | 9月 | 金性 | 陰 |
| 戌 | 10月 | 土性 | 陽 |
| 亥 | 12月 | 水性 | 陰 |
陰占(いんせん)の命式の出し方

うさ先生
生年月日から年の干支、月の干支、日の干支がでてくるの。それを陰占(いんせん)っていうよ。
陰占は万年歴(まんねんごよみ)からだせるよ。
年、月、日の干支が分かるアプリを紹介するね。すごく便利なので、干支に慣れるためにもダウンロード(インストール)してね。
陰占は万年歴(まんねんごよみ)からだせるよ。
年、月、日の干支が分かるアプリを紹介するね。すごく便利なので、干支に慣れるためにもダウンロード(インストール)してね。

うさ先生
例えば1995年6月16日生まれの人だったら、下記の干支の所を見ればいいの。


うさ先生
これを年、月、日の陰占にあてはめていくと下記みたいになるよ。
日 月 年
16 6 1995
天干(てんかん)→ 戊 壬 乙
地支(ちし) → 寅 午 亥

うさ先生
できたかな?
ここで気を付けないといけないのは、月初めが1日じゃなくて、説入り日が月初めになるっていうこと。
下記の二十四節気(にじゅうしせっき)になるよ。
ここで気を付けないといけないのは、月初めが1日じゃなくて、説入り日が月初めになるっていうこと。
下記の二十四節気(にじゅうしせっき)になるよ。
| 月 | 二十四節気 |
|---|---|
| 1月 | 小寒(しょうかん) |
| 2月 | 立春(りっしゅん) |
| 3月 | 啓蟄(けいちつ) |
| 4月 | 清明(せいめい) |
| 5月 | 立夏(りっか) |
| 6月 | 芒種(ぼうしゅ) |
| 7月 | 小暑(しょうしょ) |
| 8月 | 立秋(りっしゅう) |
| 9月 | 白露(はくろ) |
| 10月 | 寒露(かんろ) |
| 11月 | 立冬(りっとう) |
| 12月 | 大雪(だいせつ) |

うさ先生
1995年6月だったら、6日の芒種からが6月の月干支(壬午)になるの。
5日までに生まれた人だったら、5月の立夏の月干支(辛巳)になるよ。
説入り日は年によって変わるから万年歴で確かめてね。
5日までに生まれた人だったら、5月の立夏の月干支(辛巳)になるよ。
説入り日は年によって変わるから万年歴で確かめてね。
蔵干(ぞうかん)の出し方

うさ先生
次に蔵干(ぞうかん)というのを出してみよう。
十二支のなかには最大3つまでの十干を内蔵しているの。それを蔵干というの。
蔵干は全部で二十八個あるから、二十八元(にじゅうはちげん)っていうの。下記が二十八元表だよ。
十二支のなかには最大3つまでの十干を内蔵しているの。それを蔵干というの。
蔵干は全部で二十八個あるから、二十八元(にじゅうはちげん)っていうの。下記が二十八元表だよ。
| 十二支 | 初元 | 中元 | 本元 |
|---|---|---|---|
| 子 | 癸 | ||
| 丑 | 癸 9 | 辛 3 | 己 |
| 寅 | 戊 7 | 丙 7 | 甲 |
| 卯 | 乙 | ||
| 辰 | 乙 9 | 癸 3 | 戊 |
| 巳 | 戊 5 | 庚 9 | 丙 |
| 午 | 己 19 | 丁 | |
| 未 | 丁 9 | 乙 3 | 己 |
| 申 | 戊 10 | 壬 3 | 庚 |
| 酉 | 辛 | ||
| 戌 | 辛 9 | 丁 3 | 戊 |
| 亥 | 甲 12 | 壬 | |

うさ先生
二十八元は初元、中元、本元があって、となりの数字は説入り日からの日数になるの。
1995年6月だったら、6日が説入り日だから、16日だったら、16-6で10日経ってるから、10日目の地支の二十八元を出してみよう。
1995年6月だったら、6日が説入り日だから、16日だったら、16-6で10日経ってるから、10日目の地支の二十八元を出してみよう。
うさ先生、蔵干になると、よく分からなくなってきました。

ねこにゃん

うさ先生
大丈夫。ひとつずつやっていけばできるよ。
さっきの1995年6月16日の命式でやってみよう。
年支の亥は初元、中元が12日間、残り本元だよね。説入り日から10日経過していて12日以内に入るから、初元の甲が亥の二十八元になるよ。
月支の午は初元、中元が19日間、残り本元だから、中元の己が午の二十八元。
日支の寅は初元が7日間、中元が7日間、残り本元で、初元の7日は過ぎてるから中元の丙が寅の二十八元になるの。
蔵干は命式の〇のところに入るの。
さっきの1995年6月16日の命式でやってみよう。
年支の亥は初元、中元が12日間、残り本元だよね。説入り日から10日経過していて12日以内に入るから、初元の甲が亥の二十八元になるよ。
月支の午は初元、中元が19日間、残り本元だから、中元の己が午の二十八元。
日支の寅は初元が7日間、中元が7日間、残り本元で、初元の7日は過ぎてるから中元の丙が寅の二十八元になるの。
蔵干は命式の〇のところに入るの。
日 月 年
16 6 1995
天干(てんかん)→ 戊 壬 乙
地支(ちし) → 寅 午 亥
〇 〇 〇
分かった!今出した二十八元を〇のところに入れていけばいいんだね。

ねこにゃん
日 月 年
16 6 1995
天干(てんかん)→ 戊 壬 乙
地支(ちし) → 寅 午 亥
丙 己 甲

うさ先生
すごい!やったね。
これで陰占の命式ができあがったよ。
これで陰占の命式ができあがったよ。

うさ先生
実は算命学の命式を簡単に出せるアプリがあるの。それを紹介するね。
冬至節で出したいときは 自然法算命学 でだしてみてね。
冬至節で出したいときは 自然法算命学 でだしてみてね。
うさ先生どうもありがとう!
算命学の歴史から陰占の出し方まで楽しく学べました。
算命学の歴史から陰占の出し方まで楽しく学べました。

ねこにゃん
まとめ
算命学の歴史から陰占の出し方などについて書いてみました。
算命学はまずは精神ありきで陽占の方が大切とおっしゃる先生もいましたが、魂を表すのは陰占なのです。
最初は陰占は苦手意識があったのですが、今は陰占の方が好きになりました。
もちろん陽占も大切なのでまた陽占の出し方や意味など書いていきますね。